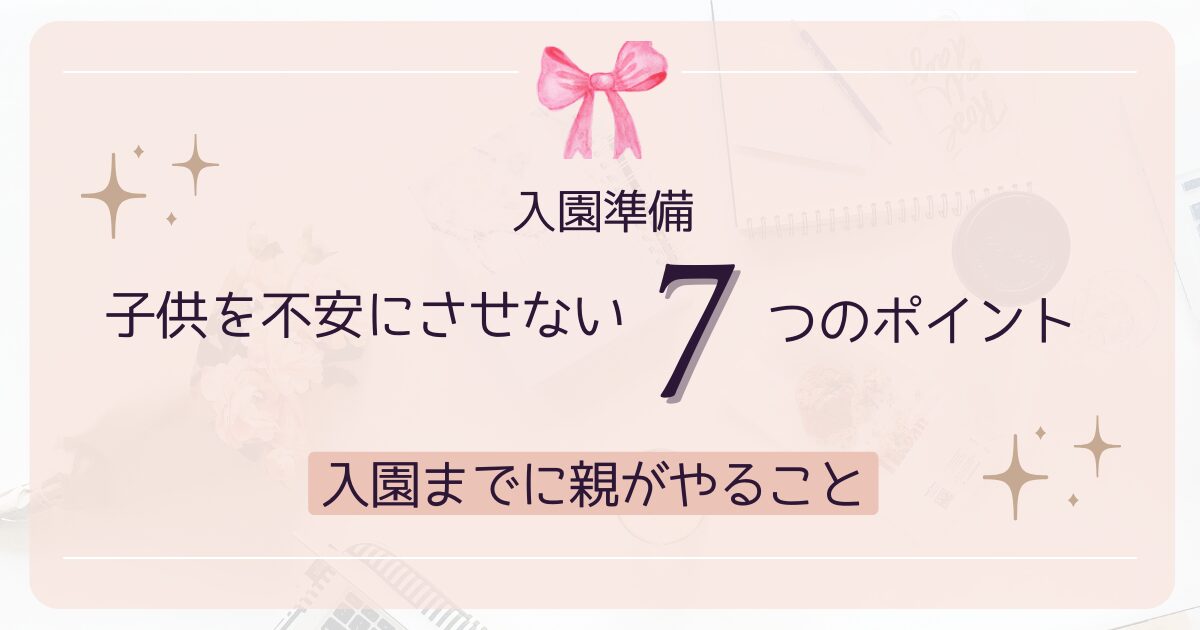✨お子さんが保育園に通う姿を想像するだけで、ワクワクドキドキしますね✨
しかしその反面、入園が迫ってくると同時にお父さんお母さんの不安も高まってくると思います。
今回のテーマは、【保育園入園前】
幼稚園に入園するお子さんのお父さんお母さん、共通する部分もありますのでぜひお読みください。
お子さんの入園に当たり、持ち物の準備もたくさんあると思いますが、もう一つ大事な準備があります。
それは、お父さんお母さんの『心の準備』です。
心の準備がままならないと、イライラしたり焦ってしまいますよね。そのイライラや焦りはそのままお子さんへと伝わってしまい、お子さんは不安な気持ちになってしまいます。
この記事では、お父さんお母さんの不安、イライラや焦りが少しでも軽減され、お子さんが安心して保育園へ通うことができるようになるためのポイントを7つお話します。
これから保活を始めようとお考えの方も、ヒントになることがたくさん詰まっています。最後までお見逃しなく!
不安を取り除く7つの確認
1.哺乳瓶に徐々に慣れる
0歳児入園をされる場合、完全母乳のお子さんもいます。完全母乳のお子さんは、哺乳瓶で飲ませようとしても哺乳瓶の口を嫌がり、飲んでくれないことが多々あります。
保育園では、粉ミルクではなく、搾乳した母乳を持参してくださいという園が多いと思いますので、哺乳瓶に入れて飲めるよう、入園前に少しづつ練習をして欲しいです。又、お母さんもお仕事が始まると母乳の出が悪くなったり、搾乳する時間がなくなることも予想されますので、粉ミルクも徐々に慣らしていくことをおすすめします。
★【電動搾乳機】
2.絵本に触れる
保育園に入園すると、遊ぶ前、給食を食べる前、お昼寝の前など、活動を切り替える際に絵本を読むことが多いです。
お家で見たことがある!ママに読んでもらったことがある!と思うだけでお子さんは安心します。なるべくたくさんの絵本に触れて、少しでもお子さんが安心できる環境を整えてあげたいですね。
どの保育園でも、同じような絵本を読んでいると思いますので、参考までに保育園で読まれている絵本を紹介します。
📚 【0歳児絵本】

📚 【1歳児絵本】

📚 【2歳児絵本】
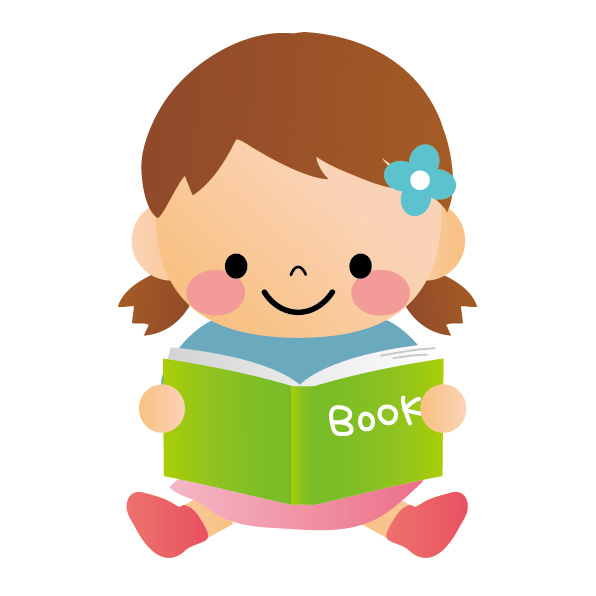
📚 【3歳児絵本】
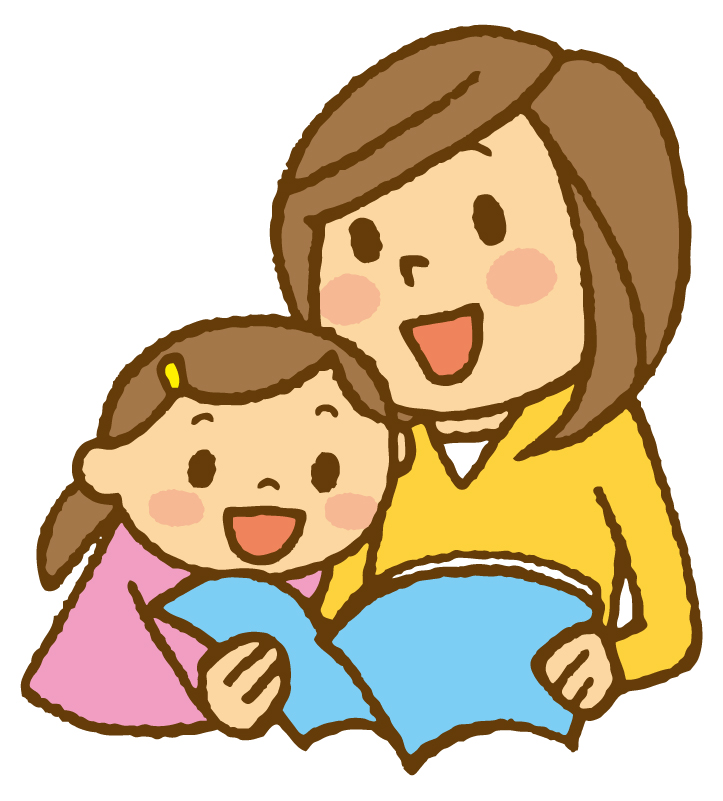
📚 【4歳児絵本】

📚 【5歳児絵本】
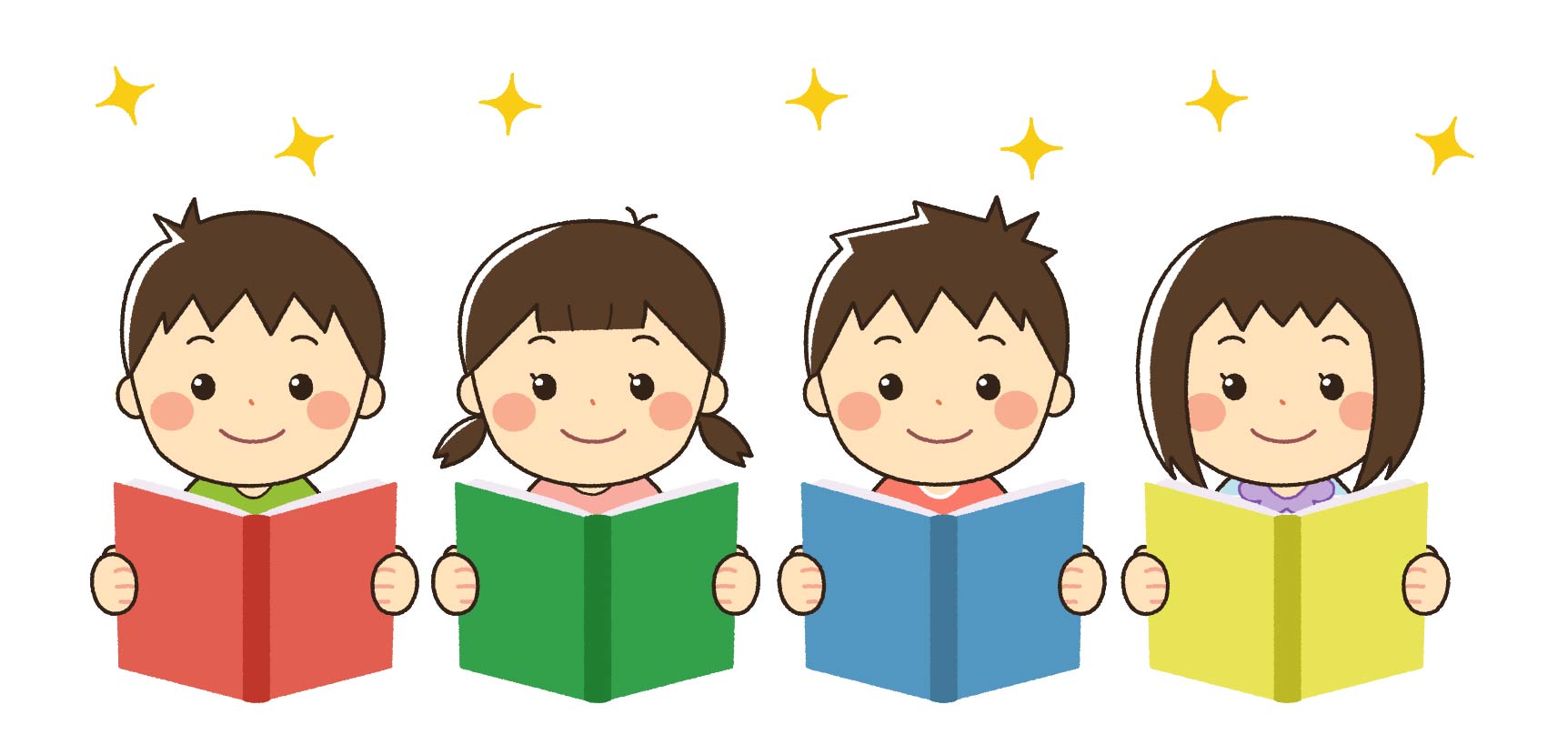
3.入園する保育園の周りをお子さんと一緒に散歩をする
抱っこやベビーカーで散歩をしても、歩いて散歩をするのでも、自転車でゆっくり回るのでも構いません。保育園周辺をお子さんと一緒に散歩をすることをおすすめします。
子どもはいつもと違う、何か違う、新しい場所となると、大人が思っている以上に雰囲気を感じ取り、不安を示すお子さんは多いものです。
歌を歌ったり、楽しい雰囲気で、「こんなのがあるんだね~」と保育園に通う道に慣れておくとお子さんも安心しますね。
★【エルゴ】エルゴベビーオムニブリーズは多くの保育園ママが愛用しています
★ 【サイベックス メリオ カーボン 2025】サイベックスベビーカーも保育園ママ達に人気!片手で開閉できるようになりました!
電動自転車は本当に必要?
今は、電動自転車が主流になっていますが、電動自転車は高額なので考えてしまいますよね。
迷ったらチェックしてみてください!
□ 坂や信号が多い
□ ママが送迎をする
□ 子どもを2人以上載せる
□ 体力に自信がない
□ 足腰の筋力が弱い
□ 買い物にも使用する
私事ですが、私が子育てをしていた頃は電動自転車なんていうものがあったのか?と思うほど子どもを2人乗せ、1人おんぶをして普通の自転車に乗っていました。若さでしたね。今思うと考えられませんが…。
普通の自転車は、走り出しが大変です。走り出しにふらついて転びそうになることもありましたね。電動自転車は高額ですが、毎日の事、安全面等考慮し、購入する、しないを検討されてみてください。
★ 【Panasonic パナソニック ギュット・クルーム・EX】
※雨の日通園に欠かせないアイテムを紹介します。
★【ベビーカー用レインカバー】
★【子供用ヘルメット】 自転車登園には必須アイテム!マグネットバックルで子どもでも簡単にかぶれます。
★【自転車子供載せレインカバー】
★【サイクルレインコート 】大きなひさしで視界を守り、顔もガードできる!袋付きなので、使用後の始末が簡単なのも嬉しいですね。
★【サイクルレインコート 】パパが送迎することも!持っていると安心です。
★レインバイザーで雨の日の自転車通勤を快適に!

4.入園する保育園周辺の公園に遊びに行く
保育園周辺の公園に行くと、もしかしたら通う保育園の子ども達が遊んでいるかもしれません。
どんな子ども達がいるのか、先生はどんな先生なのか、一緒に遊んだり、お話することもできるかもしれません。
一緒に遊べない赤ちゃんでも、声を聴いたり、賑やかな雰囲気を感じ取ることができますね。
保育園の子ども達が公園で遊ぶ時間帯は、0歳から2歳児は9時半~11時、3歳から5歳児は10時~11時半位の間で外遊びをしている保育園が多いと思いますので、ぜひ行ってみてください。
【日本サブスク大賞2024受賞】知育玩具のサブスクリプション 【Cha Cha Cha】5.家から保育園までの通園路の確認をする
子どもは、急にトイレに行きたくなることもあります。
ご自宅から保育園に行く間に、トイレはどこにあるのか、確認しておくことをおすすめします。コンビニがあるから大丈夫!と思っていても、使わせてもらえないお店もあります。公園のトイレも汚いと嫌がるお子さんもいますので、使える場所の確認が必要です。
また、普段は自転車で通う場合も、雨の日は車やバスを利用することがあるかもしれません。保育園周辺の駐車場、止められる台数、バスの時刻表、混雑具合なども確認しておくことをおすすめします。
この確認は、時間に余裕を持って登園していただきたいからです。
時間に余裕がないと、お子さんを急がせたり、普段は気にならないことでもイライラしてしまうことありますよね。お父様お母様のイライラは子どもは敏感に感じ取ります。すると登園時に泣いたり愚図ったり、余計に悪循環になってしまいますので、時間に余裕を持って登園できるよう、交通機関の確認をお願い致します。
6.保育園・幼稚園は楽しいよ
初めて通う保育園、お子様は楽しみと不安が行ったり来たりだと思います。
少しでも保育園に興味が持てるように絵本で読み聞かせをするのも効果的です。
📚 【ほいくえんのいちにち】
★保育園はどんなところ?何をするの?どんな楽しいことがあるんだろう!とワクワクさせてくれる絵本です。入園前だけでなく、入園後、保育園に行きたくないなぁ、と登園を渋るお子様にもおすすめの絵本です。
📚 【ようちえんのいちにち】
★幼稚園の子どもたちは、どんな一日を過ごすのかな? お友だちと乗る通園バス、歌やダンスの時間、楽しみなお弁当の時間、ワクワクがいっぱいの幼稚園の一日を紹介する絵本です。
★保育園ではこんな玩具で遊んでいます!保育園にある玩具が1つでもお家にあると子どもは安心しますね。

★【素敵な保育園の見極め方】これから保活を検討される方、こちらも合わせてご覧ください😊
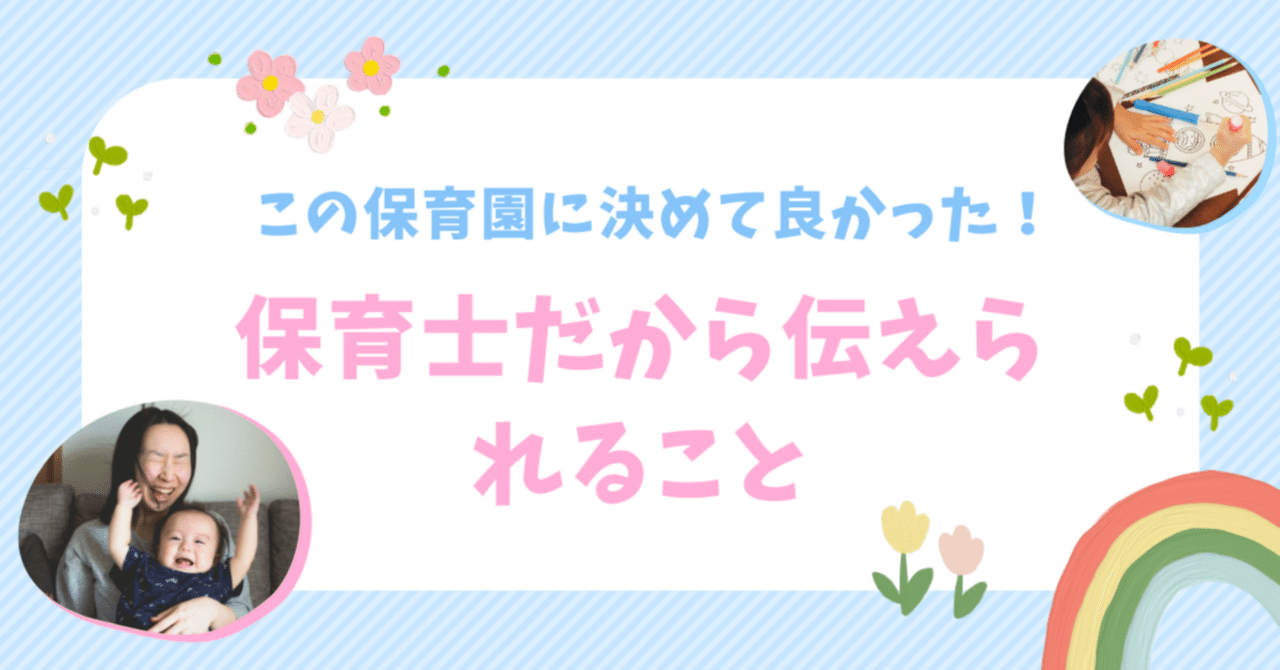
7.入園に関する持ち物準備は子どもと一緒に行う
持ち物の準備をお子さんと一緒に行うことで、保育園に興味や関心を持つことができます。
お名前シールやスタンプで記名をするご家庭が多いと思いますが、一緒に貼ったり押したりすることで、自分の持ち物を確認することができます。と同時に、鞄のどこに入っているのかを把握することで、保育園でのお支度をスムーズに行うことができます。
保育園でのお支度をスムーズに行うことができると、自信が付きますので、次々と色々なことに挑戦するようになり、保育園生活を楽しむことへと繋がっていきます。
★【お名前シール】忙しいママの必需品ですね!かわいい・かっこいいが揃っています!
★【おむつスタンプ】ポンポン押せて簡単!パパにも頼みやすいですね!
★【お名前シールのママメリット&子供メリット!】
合わせてお読みください↓
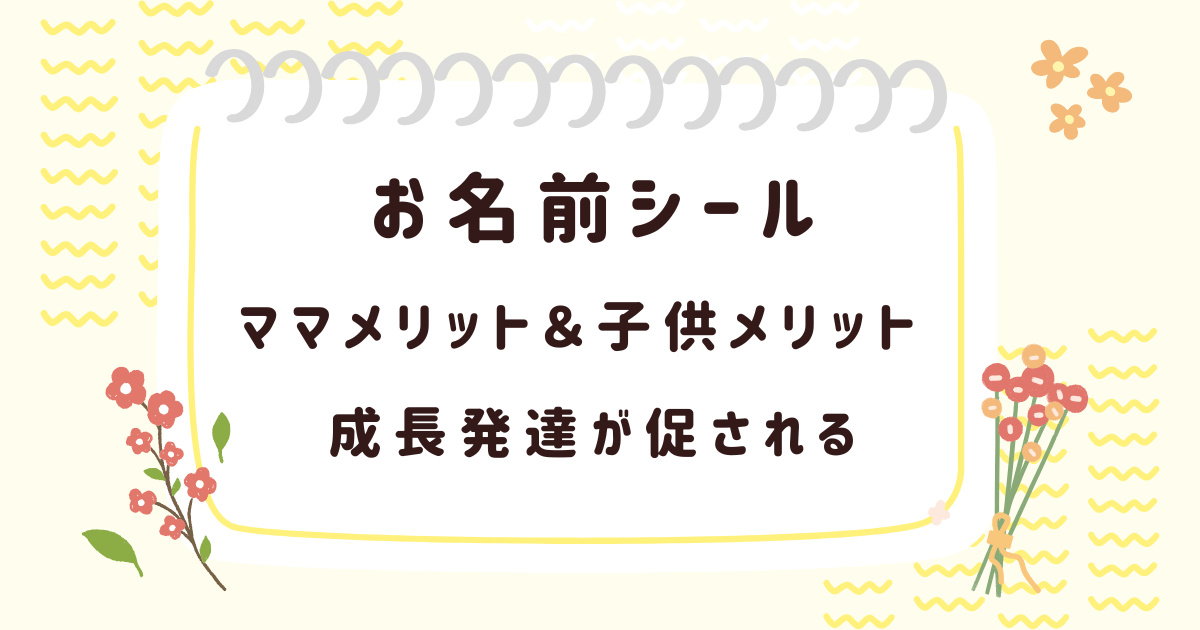
ママバッグの準備
保育園によっては、おむつのサブスクやエプロンの貸し出し等、保護者の負担を減らそうという保育園も増えていますが、そうでない場合は、特に0,1,2歳児は毎日持参する荷物が多いです。おむつ5~10枚、エプロン2~3枚、着替えはお子さんの汚し具合、食べこぼし具合により枚数は異なります。
更にヘルメットや抱っこ紐を入れる等ありますと、大きなママバッグが必要です。
★ 【マザーズバック】
★ 【防水お昼寝バッグ】 バッグの外側にはっ水、内側には防水加工を施しているため、汗やおねしょで濡れたものでも安心して持ち帰ることができるのは嬉しいですね。
★入園式の服装、どんな服を着ればいいの?かわいい・かっこいいをご紹介します!

まとめ 『大丈夫!何とかなる!』
保育園入園の心の準備についてお話してきました。
ママやパパの不安がお子さんの不安に繋がりますので、『大丈夫!何とかなる!』と大きな心でお子さんを信じて欲しいと思います。
子どもは大人以上に敏感さを持つ半面、柔軟さも備わっていますので、あまり心配なさらず見守ってあげてくださいね。
そして入園後、心配なことがありましたら遠慮なく保育士に相談して欲しいと思います。
素敵な保育園・幼稚園生活となりますように🎀